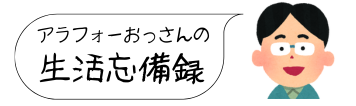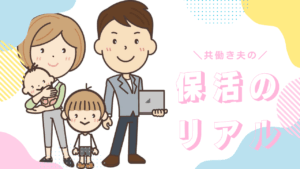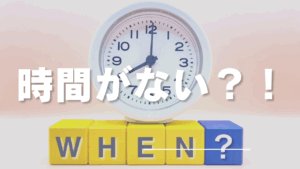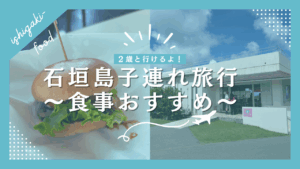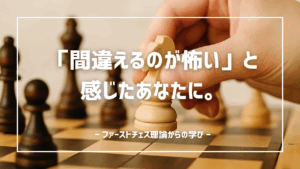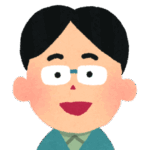 ナガタニ
ナガタニ保活?なんだそれ?
いま0歳児育児を楽しんでいるあなた。
とにかく産まれてきてくれた我が子はかわいいか。
あぁ、かわいいさ。私もそう思います。(一介の親ばかおっさん)
ただ、かわいいかわいいとだけ言っていられないのが育児。
予防接種、定期健診などなど、日常のお世話に以外にもたくさんやることのある育児。
そんな中でも、結構時間がかかる上に重要なのが、保活こと保育園入園活動。
時の流れはあっという間なので、気づいたら翌年度の4月がやってくる。
そう、共働きの世帯では4月が来れば我が子を保育園に入れないといけません。
「保育園なんて、だれでもはいれるんでしょ?」なんて思っていたら、それは甘い。
ルノアールのココアより甘い。(歴史を感じる表現)
そして夫である我々がそんな認識で生活していたとしたら・・・
それは間違いなく家庭崩壊への序章です。
スケジュール的に、実際の申し込みや見学に行けないとしても、
情報収集はできますし、なにより勉強はできます。
知識レベルを妻と合わせていくことで、日常の会話で齟齬がなくなりますし、それではじめて協力して育児をできているということになるのではないでしょうか。
夫婦で動かないと厳しい…それが第一子での保活を終えた今の正直な感想です。
この記事では、共働きの夫である私が、実際に保活を経験して学んだ「やるべきこと・考えるべきこと」をリアルにまとめました。
これから保活を始めるパパ、夫婦で保活を協力して進めたいご家庭に向けて、役立つ情報をお届けします。
保活とは?パパも知っておくべき基本情報
保活とは、「子どもを希望の保育園に入れるために行う情報収集や手続き、準備全般のこと」です。
保育園探しから書類の準備、見学、申請まで、夫婦で分担して進めることが大切です。
妻の希望を叶えようと、気遣ったつもりだとしても・・・
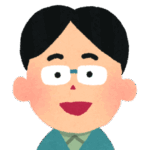
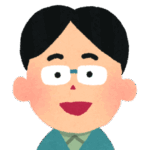
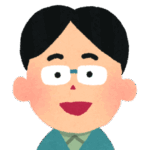
いいよ。ママの行きたいところに入れてあげようよ
この一言を発した時点で、GAMEOVERです。
家庭崩壊へのカウントダウンの針は進んだと認識してください。
「自分事」として、一緒に考え調べること。
夫婦の連携が結果を左右するので、ぜひ頑張って下さい!
✅ 保活でパパが知っておきたい「やるべきこと」はこちら:
- 自治体の「指数(点数)」制度を確認する
- 希望の保育園をリストアップ&見学する
- 希望園の倍率や傾向を調べて、優先順位をつける
- 就労証明書などの必要書類を会社に依頼する
- 提出期限や手続き方法を確認してスケジューリングする
- ママと情報共有し、役割を分担して進める
最初は何から始めればいいか戸惑いましたが、
「まずは役所で情報を集める」「気になる園の倍率を知る」といったことから始めると、全体の流れが見えてきます。
保活のスケジュール感|実際に動き始めた時期と理由
うちの子が入園するために、動き始めたのは0歳の6月ごろでした。
「早すぎるかな?」と思いましたが、実際に役所で話を聞くと、
園見学や必要書類の準備、申請までの流れが意外とタイトで驚きました。
✅ 保活の流れ(うちの場合の実例)
- 6月:保活開始。役所で説明を聞く/指数の仕組みを把握
- 7月:保育園の候補を調査・見学予約を開始
- 8月:園見学ラッシュ/倍率などもチェック
- 9〜10月:希望園の絞り込み・就労証明など書類準備
- 11月:申請書類の提出(※自治体によって異なります)
- 翌年2〜3月:結果通知 → 必要に応じて二次募集の検討
- 4月:入園・慣らし保育スタート
自治体や年齢クラスによって時期は多少前後しますが、
少なくとも夏前には情報収集と見学予約を始めるのがおすすめです。
指数を知る|保活で最重要の「点数制度」とは?
保育園の入園選考では、申請者に対して「指数(点数)」がつけられ、その合計で優先順位が決まります。
この仕組みを知らずに保活を進めると、高倍率の園ばかり選んでしまったり、点数的に不利な条件を見逃したりすることがあります。
✅ まず知っておきたい「指数の基本」
- 共働き(フルタイム)は基本点が高い
- ひとり親・兄弟が同園在籍などで加点がある
- 保育園ごとに必要な点数の目安が異なる
- 自治体のHPか窓口で一覧を入手できる
例えば、横浜市を例にすると、そもそもまずは就労状況によってA〜Fのランクに分類され、これが保育所等利用調整(いわゆる点数)の基準となります。
同じランク内での差を調整するために、加点・減点制度も設けられています。
就労時間だけでなく、保育歴や預け先などもポイントに影響するのが特徴です。
(例)横浜市 令和7年度|就労ランクと加点・減点制度(抜粋)
📌 就労状況によるランク(A〜F)
| ランク | 就労状況 |
|---|---|
| A | 月20日以上かつ月160時間以上の就労 |
| B | 月20日以上かつ月140〜159時間の就労 |
| C | 月16日以上かつ月96時間以上の就労 |
| D | 月16日以上かつ月64〜95時間の就労 |
| E | 月12日以上かつ月64時間以上の就労 |
| F | 月64時間以上の就労(上記に該当しない) |
📌 加点・減点制度(主な例)
| 内容 | 点数 | 備考 |
|---|---|---|
| 親族(65歳未満)に預けている | -1 | 非保育施設の預け先 |
| 認可保育所からの転園(通常) | -1 | 転居・きょうだい同一希望を除く |
| 小規模保育等の卒園児 | +5 | 卒園証明書が必要 |
| 小規模保育等を現在利用中 | +1 | 在園証明書が必要 |
| 育休で一時退園→復職時に再申請 | +5 | 利用期間の証明資料が必要 |
| 64時間以上の有償預かり保育利用 | +3 | 契約書等の証明資料が必要 |
※点数は全体の優先度に影響しますが、最終的な調整は同ランク内で行われます。
このように、点数制度は自治体によって大きく異なります。
まずはお住まいの役所で「選考基準表」を入手して確認しましょう。
とはいえ、点数はある程度決まっていて、自分たちで増やせる部分は限られます。
「点数稼ぎが保活の第一歩」なんて言われることもありますが、私の経験ではそこまでの重要性は感じませんでした。
それよりも、園の雰囲気や送迎のしやすさなど、中身を調べることに時間を使う方が現実的だと感じました。
必要以上の点数稼ぎより、倍率を見よう
点数が高ければ確実に入れるわけではなく、実際は「希望する園の倍率」が非常に重要です。
人気園に申請が集中していると、満点でも落ちることがあります。
✅ 倍率のチェック方法と園選びのコツ
- 自治体によっては「前年度の倍率」を公開している
- 駅近や新設の園は特に高倍率
- 徒歩圏の小規模園は狙い目のケースも
- 複数希望を出す際は「滑り止め園」も必須
実際、わが家も「一番近い園」にどうしても入れたくて、最初はそこを第一希望にしていました。
ただ、よく見るとその園は募集人数が少なく倍率も高め。
見学を重ねるうちに、「実際に通わせたい」と思える園は3園ほどに絞られました。
とはいえ、申請時には落選の恐怖に打ち勝てず、10園を希望順位つきで提出。
結果的に、第3希望の園に決まりましたが、少数精鋭で申し込んで落ちてしまうリスクをとるよりも、多く滑り止めを出すことも大事です。
希望園を絞りすぎるより、「この園もありかな」と思える候補を広げつつ、倍率や受かりやすさも見ておくのが現実的だと感じました。
希望園の見学とランキングづけ
Webサイトや口コミだけではわからないことも多いため、実際に園に足を運ぶ「見学」が保活の要だと感じました。
夫婦で行けると、送迎や距離、雰囲気などの感じ方をすり合わせやすくなります。
✅ 園見学でチェックしたポイント
- 先生たちの雰囲気・子どもへの声かけ
- 保育室や園庭の広さ・清潔感
- お昼寝・給食・トイレの方針
- 朝夕の送迎ルートの安全性
- 通わせる期間を見越した通いやすさ
「家から一番近い園」は見学したら合わなかったり、
「少し遠い園」が意外と良かったり…。実際に見ることの大切さを痛感しました。
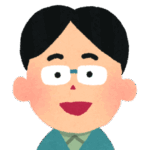
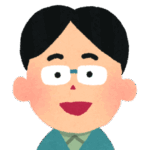
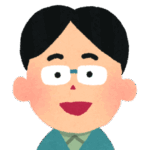
先生たちの雰囲気と、園の綺麗さ。あとは通わせやすさは大事ですぞ!
毎日の送り迎えが遠いと、本当につらい!
就労証明書は早めに!会社対応に要注意
保育園の申請に必要な「就労証明書」は、自治体ごとのフォーマット指定があることがほとんどです。
会社によっては作成に時間がかかる場合があるので、早めの依頼が鉄則です。
✅ 就労証明で注意すべきポイント
- 自治体指定のフォーマットがあるか確認
- 記入ミスがあると差し戻しになることも
- 夫婦それぞれ1通ずつ必要
- 会社によっては発行に1〜2週間かかる
僕は最初「会社に言えばすぐもらえる」と思っていたんですが、書類の差し戻しを2回経験し、締切ギリギリになりました…。
おそらくPDFでくれるので、印刷も忘れずに・・・
まとめ|保活で一番大事だったのは「夫婦の連携」
いろんな園を調べたり、書類を揃えたりと、保活にはやることがたくさんあります。
でも、実際に終えてみて一番大切だったと感じるのは、「夫婦で役割を分担して動いたこと」です。
✅ 振り返って思う「成功ポイント」
- 早めに動いてスケジュールに余裕を持てた
- 見学を夫婦で分担して情報を共有できた
- 点数や倍率を冷静に分析できた
- パパ視点でも積極的に関われた
はじめは右も左もわからなかったけれど、ネットと役所で地道に調べた情報と、パートナーとの連携があったからこそ乗り切れました。
これから保活に取り組む方の参考になればうれしいです!
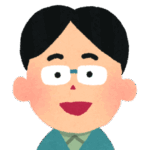
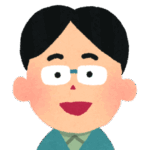
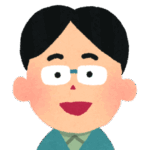
保育園は、子どもの成長がぐっと早まる気がします